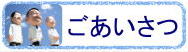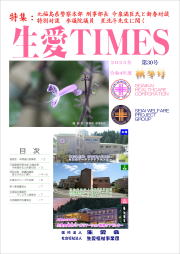| 介護保険制度について |
介護保険とは
保険加入者
サービス利用の手続き
要支援・要介護度
施設サービス
地域密着型サービス
居宅サービス
利用者負担 |
 |
|
|
| 介護保険とは‥ |
| 介護保険制度は、高齢化の急速な進展と増加する介護の費用、多様化するニーズへの対応を目的とし、平成12年度4月からスタートしました。それまでは行政
がサービスを決定していましたが、利用者自身がサービスを選択できるようになり、効率的で良質なサービスを受けることができるようになりました。 |
 |
 |
介護保険制度は平成18年4月1日に改正され、地域に根ざした在宅ケアと認知症ケアの支援の強化、介護予防の導入とリハビリテーションの推進がなされました。また、改正により従来の要支援が、要支援1と要支援2へと区分されました。要支援1・2の方は要介護状態とならないように予防を目的とした給付、要介護1〜5の方は従来の介護サービスの給付が受けられます。 |
|
|
| 保険加入者 |
第1号被保険者(65歳以上の方)
〜市町村から要介護認定を受けた方がサービスを受けることができます。
第2号被保険者(40歳から64歳以上で医療保険に加入されている方)
〜介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で要介護認定を
受けた方は、サービスを受けることができます。 |
| ※特定疾病 |
|
①筋萎縮性側索硬化症 |
⑩パーキンソン病 |
|
②後縦靱帯骨化症 |
⑪閉塞性動脈硬化症 |
|
③骨折を伴う骨粗鬆症 |
⑫慢性閉塞性肺疾患 |
|
④シャイ・ドレーガー症候群 |
⑬慢性関節リウマチ |
|
⑤脊髄小脳変性症 |
⑭糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び |
|
⑥脊柱管狭窄症 |
糖尿病性網膜症 |
|
⑦初老期における痴呆 |
⑮両側の膝関節又は股関節に著しい変形 |
|
⑧早老症 |
を伴う変形性関節症 |
|
⑨脳血管疾患 |
⑯末期がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの) |
|
|
| サービス利用の手続き |
①申請〜介護や支援が必要になったら
住んでいる市町村に要介護認定
の申請をします。
②訪問調査〜認定調査員が申請者の家庭
等を訪問して、人の心身の状況
を調査します。
③一次判定〜認定調査員の調査内容を基
に、一次判定が行なわれます。
(全国一律の基準で行なわれます)
④二次判定〜認定調査員が記入する特記
事項と、主治医が記入する主治
医意見書をもとに、介護認定調
査会による要介護度の二次判定
が行なわれます
⑤判定〜二次判定を受けて、市町村が要
介護度の判定を行ないます。
⑥ケアプランを作成〜認定を受けたら、
「居宅サービス」か「施設サービ
ス」を選び、それぞれのケアマ
ネジャ−と相談してケアプラン
を作成します。
⑦利用〜ケアプランにもとづいて、各種
サービスを利用します。
|

 |
|
| 要支援・要介護度 |
| 状態 |
説明 |
| 要支援1 |
要介護とは認められないが、社会的支援を要する状態。 |
| 要支援2 |
生活の一部分について部分的介護を要し、認知症とは認められない状態。 |
| 要介護1 |
生活の一部分について部分的介護を要し、認知症と認められる状態。また、末期のガン患者の方。 |
| 要介護2 |
軽度の介護を要する状態。 |
| 要介護3 |
中等度の介護を要する状態。 |
| 要介護4 |
重度の介護を要する状態。 |
| 要介護5 |
最重度の介護を要する状態。 |
|
 |
※要支援1・2の方は予防給付の対象となり、要介護度1〜5の方は介護
給付の対象となります。予防給付と介護給付の併給はできません。 |
|
| 施設サービス ※赤文字は当法人・事業団にて受けられるサービスです。 |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
|
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象となります。食事や排泄などの日常生活を営む上で必要な支援や、機能訓練が受けることができます。 |
| 介護老人保健施設 |
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いた介護が必要な方が対象となります。医学的な管理のもとで、介護やリハビリテーションが受けることができます。 |
| 介護療養型医療施設 |
病状は安定しているが、長期にわたる療養が必要な方が対象となります。療養設備の整った環境の中で介護を受けることができます。 |
|
  |
|
地域密着型サービス
※赤文字は当法人・事業団にて受けられるサービスです。 |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象となります。食事や排泄などなどの日常生活を営む上で必要な支援や、機能訓練が受けることができる、小規模(30人未満)の特別養護老人ホームです。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護
(小規模有料老人ホーム等) |
リハビリテーションや看護が必要な方が入所し、日常生活の訓練を行う、小規模(30人未満)の特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設です。 |
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
比較的安定した状態の認知症状を抱える方が、日常生活上の世話や機能訓練を、共同生活の中で行う施設です。 |
認知症対応型通所介護
(認知症対応デイサービス) |
比較的安定した状態の認知症状を抱える方が、日常生活上の世話や機能訓練を、通いながら行う施設です。 |
| 小規模多機能型居宅介護 |
「通い」を中心に利用者の状態や希望、家庭の事情に応じて「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できる施設です。 |
| 夜間対応型訪問介護 |
自宅での生活を安心して続けられるように、夜間を含めて、24時間365日定期巡回と通報による対応を、随時行います。 |
|
居宅サービス
※赤文字は当法人・事業団にて受けられるサービスです。 |
| (1)予防給付等サービス |
| 介護予防サービス等の種類 |
サービスの内容 |
訪問型サービス
(福島市サービス) |
ホームヘルパーが訪問し、介助や支援などを行ないます。 |
通所型サービス
(福島市サービス) |
デイサービスセンターで介護や機能訓練受けることができます(共通的サービス)。また、運動機能の改善、栄養状態の改善、口腔機能の改善からサービスを選ぶことができます。 |
| 介護予防訪問看護 |
看護師などが訪問し、点滴の管理や床ずれの手当てを行なったりします。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション |
リハビリテーションの専門家が訪問し、リハビリテーションを行ないます。 |
介護予防
居宅療養管理指導 |
医師や薬剤師が訪問し、療養上の管理・指導を行ないます。 |
| 介護予防訪問入浴介護 |
訪問入浴車などで訪問し、入浴の介助を行ないます。 |
介護予防通所
リハビリテーション |
介護老人保健施設や病院で、日帰りのリハビリテーションが受けられます(共通的サービス)。また、運動機能の改善、栄養状態の改善、口腔機能の改善からサービスを選ぶことができます。 |
介護予防短期入所
生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期入所して、介護や機能訓練が受けられます。 |
介護予防短期入所
療養介護 |
介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護機能訓練が受けられます。 |
介護予防特定施設
入所者生活介護 |
有料老人ホームなどに入所して、介護や機能訓練が受けられます。 |
| 介護予防福祉用具貸与 |
日常生活を支援する用具の貸与で日常生活の便宜を図ります。
(車椅子や特殊寝台など、一部貸与されないものがあります) |
| 介護予防福祉用具購入 |
入浴や排泄のための用具の購入にかかる費用を給付します。 |
| 介護予防住宅改修費 |
小規模な住宅改修に対して、その費用を給付します。 |
| 介護予防支援 |
要支援者の要望や状況にあったケアプランが地域包括支援センターにて作成され、介護サービスの利用を支援します。 |
|
| (2)介護給付サービス |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
| 訪問介護 |
ホームヘルパーが訪問し、身体介助や生活援助などを行ないます。 |
| 訪問入浴介護 |
訪問入浴車などで訪問し、入浴の介助を行ないます。 |
| 訪問看護 |
看護師などが訪問し、点滴の管理や床ずれの手当てを行なったりします。 |
| 訪問リハビリテーション |
リハビリテーションの専門家が訪問し、リハビリテーションを行ないます。 |
| 居宅療養管理指導 |
医師や薬剤師が訪問し、療養上の管理・指導を行ないます。 |
| 通所介護 |
デイサービスセンターで介護や機能訓練が受けられます。 |
| 通所リハビリテーション |
介護老人保健施設や病院で、日帰りのリハビリテーションが受けられます。 |
| 短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期入所して、介護や機能訓練が受けられます。 |
| 短期入所療養介護 |
介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護機能訓練が受けられます。 |
特定施設入所者
生活介護 |
有料老人ホームなどに入所して、介護や機能訓練が受けられます。 |
| 福祉用具貸与 |
日常生活を支援する用具の貸与で日常生活の便宜を図ります。
(要介護度1の方は、車椅子や特殊寝台など一部貸与されないものがあります) |
| 福祉用具購入 |
入浴や排泄のための用具の購入にかかる費用を給付します。 |
| 住宅改修費 |
小規模な住宅改修に対して、その費用を給付します。 |
| 居宅介護支援 |
要介護者の要望や状況にあったケアプランをケアマネジャーが作成し、介護サービスの利用を支援します。 |
|
|
|
| |
|
| 利用者負担 |
| 要支援1・2、または介護度1〜5で認定された方で、その介護度に応じた金額の中でサービスを受けることができます。サービスを受けたときは、原則として費用の1割または2割が自己負担となります。それぞれの介護度において決められている金額を超えた場合は、超過した分の金額が実費となります。 |
| 戻る |
|
| ご意見・ご感想はhonbu@seiaikai.jpへ |
| 生愛会在宅支援課 |
福島市大笹生字向平13-1
TEL 024-555-2244(大代表) FAX 024-555-2241
|